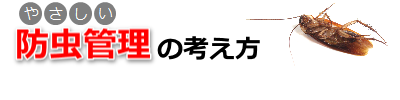ゴミムシなど

ゴミムシ・オサムシ・ハンミョウなどの仲間は、堆肥や刈り草、石の下などでよく見つかる小型の甲虫です。
よく誤解されるのですが、ゴミムシはゴミを食べるのではなく、ゴミを食べにくる他の昆虫を食べています。
また、これらの仲間は地上を素早く歩くため、歩行虫とも呼ばれています。
ゴミムシの仲間は、世界で2万種以上が知られ、日本にも数百種以上が分布しています。
多くの種は夜間に活動し、地上で生活しますが、樹上で生活する種や昼間活動する種など、生態は様々です。
生息場所は、海岸から高山まで、熱帯から極地までと、多岐にわたり、地球上のありとあらゆる場所で生活しています。
中には洞窟や土中で生活し、眼が退化したものもいます。

場所によっては、冬が近くなると大量のゴミムシが外部から侵入することがあり、製造工場や倉庫で問題となることがあります。
飲食店や小売店でも、清掃しても次の日にはまた侵入してくる大量のゴミムシに悩まされることがあります。
内部に侵入したゴミムシは、段ボールや製品、原料などの中に入り込むことがありますので、注意が必要です。
歩行虫の名の通り、地上を歩き回る徘徊性昆虫のイメージが強いゴミムシですが、5mm以下の小型のゴミムシは飛翔力に優れ、光にもよく誘引されるため、モニタリング用のライトトラップにもよく捕獲されます。
これらは工場内を飛び回り、製品に混入する恐れがあります。
滅多にないことですが、ミズギワゴミムシなどの小型のゴミムシの仲間には、内部(あるいは内部に限りなく近い箇所)で発生を繰り返すことが可能な種がいるようです。
これらは、恐らく床下で生活しているのでしょう。工場内部の壁(内壁の内側)や床材(タイルやコンクリートなど)の下、側溝などのひび割れなどから自由に出入りし、充填室や包装室などの重要エリア内に多数侵入しきます。
ミズギワゴミムシの仲間は、一般住宅でもお風呂場などでタイルや床の立ち上がりにできた隙間から見つかることがあるように、少し湿った環境を好むようです。